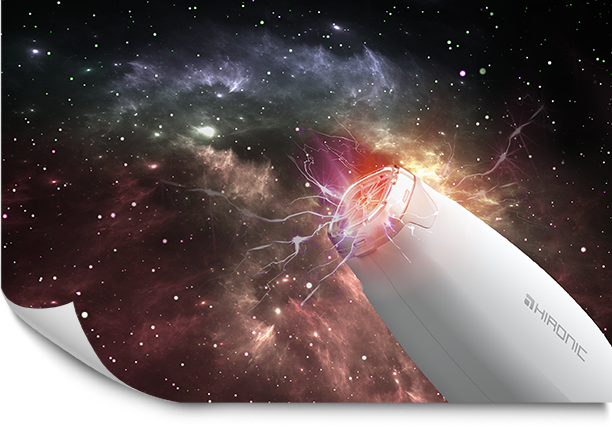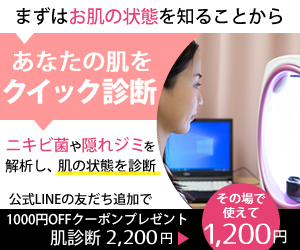ニキビの治療の保険適応内の治療は?
ニキビの治療は、赤ニキビ・黄色ニキビの炎症性皮疹の対応(急性期の治療)と、ニキビのはじまりである微小面皰、面皰(白ニキビ、黒ニキビ)の対応(維持療法、次のニキビを防ぐ)に分けられます。
ニキビの炎症性皮疹(赤ニキビ、黄色ニキビ)の治療1)
この時期の治療は、面飽を伴う炎症性皮疹が主体であり,炎症に対する積極的な治療が行われます。
炎症性皮疹に対し、アダパレン0.1%ゲル(ディフェリンゲル)という塗り薬が強く推奨されています。
使い方は、1日1回で寝る前の洗顔後に適量を赤ニキビ・黄色ニキビの部分に塗ります。
副作用として皮膚に赤みが出る症状が8割程度、灼熱感・かゆみが2割くらいの方に出現します。
それに並行して抗菌薬の塗り薬や飲み薬も使用することがあります。
塗り薬としてはクリンダマイシン,ナジフロキサシン,オゼノキサシンといった抗生剤(ニキビ菌・アクネ菌をやっつける)が多く使用されています。
過酸化ベンゾイル2.5%ゲル(ベピオゲル)という塗り薬は、抗生剤ではないですがニキビ菌を殺菌作用があり赤ニキビ・黄色ニキビを改善します。
抗生剤のクリンダマイシン1%と過酸化ベンゾイル3%を配合した塗り薬(デュアック)やアダパレン0.1%と過酸化ベンゾイル2.5%を配合した塗り薬(エピデュオ)も開発されており、これらの配合塗り薬も使われます。
飲み薬の抗生剤としてはドキシサイクリン、ミノサイクリンが使用され、アダパレンと内服抗菌剤の塗り薬や飲み薬の併用することも強く推奨されています。
これらの赤ニキビ・黄色ニキビの治療期間は最大3カ月を目安として、その後は維持期の治療へ移行します(次のニキビを抑える)。
アダパレンゲルの役割は?2)
アダパレンは、天然のレチノイド(ビタミンA)とは構造が異なりますが、レチノイド様作用があり、表皮が角化しにくくする作用があります。これにより、毛穴の角化を抑制して新たなコメドができにくくなります。
BPOの役割は?2)
過酸化ベンゾイルは、発生させるフリーラジカル(活性酸素)が殺菌作用を持っています。また、このフリーラジカルが、角層中のタンパクを変化させ角質細胞同士の結合がゆるくし角層の剥離作用(ピーリング作用)をもたらします。
アダパレン0.1%と過酸化ベンゾイル2.5%を配合した塗り薬(エピデュオ)の役割は?2)
アダパレンは、コメドができる原因である毛穴の角化を抑制し、過酸化ベンゾイルは角層の剥離作用があり毛穴が詰まりにくくする、かつ殺菌作用を持っている薬剤です。
併用することで、アダパレンの作用と、過酸化ベンゾイルの作用がお互いに相乗的に効果をもち、それぞれだけを治療で使うよりも、より高い効果をうみだします。
クリンダマイシン1%と過酸化ベンゾイル3%を配合した塗り薬(デュアック)の役割は?
アクネ菌に対する抗生剤であるクリンダマイシンは、赤ニキビや黄色ニキビの炎症性のあるニキビに対して、アクネ菌を抑えることでニキビを改善させます。
ここに、クリンダマイシンとはことなる方向から殺菌作用をもつ過酸化ベンゾイルを一緒に使うことで、クリンダマイシンだけを塗るよりも、より高い効果をもたらします。また、過酸化ベンゾイルはピーリング作用があり、それも毛穴のつまりを改善させ、ニキビの改善を促します。
ニキビの炎症性皮疹の治療は、ニキビの重症度(ひどさ、ニキビの範囲)で変わるのか?1)
ここで、もう一度ニキビの重症度を見てみましょう、以下のとおりです。
- 軽症:片顔に炎症性皮疹が5個以下
- 中等症:片顔に炎症性皮疹が6個以上20個以下
- 重 症:片顔に炎症性皮疹が21個以上50個以下
- 最重症:片顔に炎症性皮疹が51個以上
次に、ニキビの重症度ごとの治療について述べてみます。
軽症ニキビは、アダパレンやBPOゲル塗り薬、また配合塗り薬、必要に応じて抗生剤塗り薬、中等症ニキビは、アダパレン+BPO配合塗り薬、CLDM+BPO塗り薬、必要に応じて抗生剤飲み薬、重症以上のニキビは、中等症ニキビ治療に抗生剤飲み薬の治療が推奨されています。
ニキビ維持期の治療(微小面皰、面皰(白ニキビ、黒ニキビ)の対応)1)
毛穴の角質抑制作用のあるアダパレンの塗り薬、抗菌作用・ピーリング作用のあるBPOの塗り薬を使って、新たな微小面皰、面皰の発生を予防します。
まとめ
今回は、ニキビの皮膚科での治療について説明しました。
赤ニキビや黄色ニキビについては、重症度に応じて抗生剤の塗り薬、飲み薬を使用して炎症を抑える治療を行います。その後は、ニキビの初期である微小面皰、面皰をできないようにする塗り薬の治療を行っていきます。
参考文献
1) 林伸和ら. 日皮会誌 2017;127:1261.
2) 大谷 道輝. 薬局. 2017;68:88.